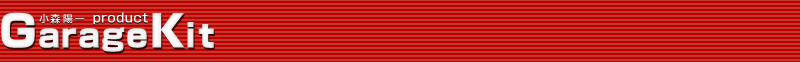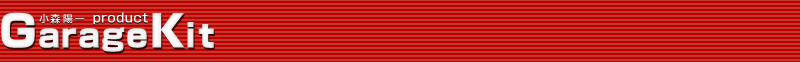上陸期に続いて二度目のヘドラ挑戦である。今回は成長期ということで、ポーズは寝そべっているのではなく二足で立っている。これだけ長い時間ガレージキットを嗜んでいると、箱を開けてパーツを見た瞬間、大体のサイズ感が分かる。(これは想像以上に大物だ)と思った。その時は単に大きさのことを想像したのだが、本当の意味での想像以上はその後の課程で嫌というほど味わうことになる。
上陸期に続いて二度目のヘドラ挑戦である。今回は成長期ということで、ポーズは寝そべっているのではなく二足で立っている。これだけ長い時間ガレージキットを嗜んでいると、箱を開けてパーツを見た瞬間、大体のサイズ感が分かる。(これは想像以上に大物だ)と思った。その時は単に大きさのことを想像したのだが、本当の意味での想像以上はその後の課程で嫌というほど味わうことになる。
キットは真ん中に太いレジンの芯があり、そこに様々な形のヒダというかヒレのパーツを貼り付けていく。考えてもみて欲しい。一枚一枚形を整え、油分を洗い落とし、しっかりと乾燥させたらサフを塗り、そこからベースの色を乗せる。これを胴体や手足、尻尾に取り付けるヒレが混ざらないように仕分けしながら進めねばならない。そりゃもう普段の三倍は時間がかかる。塗装に入る前の下準備で既に修行だったが、(いざ組み立てを)と思いきや、こちらもそう簡単にはいかなかった。うっかり取り付ける場所と順番を間違えると、二度と筆が入らない場所が生まれたり、その後のパーツが上手く組み合わなかったりする。いや、その前に、取り付ける場所がよく分からない。ヒレのパーツには番号が刻印されているのだが、取り付ける側にそれが見当たらない。まるで難解なパズルを組み立てるように、一つずつパーツを当てて位置を確かめながら作業を進めていった。
それにしてもだ。ヘドラのシルエットからこのヒレの形状とパーツの分割をどうやって見定めていったのか。しかも、型抜きのことまで考えてだ。まったく信じられない。一流の体操選手は空間認識能力が磨かれており、頭の中でイメージをすると、その通りに身体を動かすことが出来るという。それと同じようなことが原型師、杉田知宏氏の脳内で起きていたのではないか。杉田さんがどれほどこだわって造型をされるか、一度でもキットを組んだことのある諸兄ならお分かりだろう。あまりの細かさに呆れ、思わず笑ってしまうほど徹底的に造り込まれている。だが、今回のヘドラはそれともまた違う。以前、浅川さんのウーと相対した時と同じ衝撃が、この杉田ヘドラからは確かに伝わってきた。決して大袈裟に言っているのではない。紛れもなく天才の所業だと思う。
下準備や組み立てが大変なら、塗装もまた大変だった。ヘドラを塗る。怪獣好きなら分かるだろう、それがどれほど難しいことか(苦笑)ベースはタイヤブラック、その上からグリーン、グレー、ブラウンを乗せていき、淀んだ雰囲気を作った。本編映像ではナイトシーンなので、こちらはあまり塗装の参考にはならない。よってムック本などの資料から色の細部を紐解いていった。背中や尻尾にはこれでもかという毒々しい原色のイエローやレッドが乗っている。それらは基本、筆塗りで行った。ヒレの先端や内側にも同様に筆で色を乗せた。縦長の目玉はクリアパーツになっており、何層かに分けてクリアーレッドを吹きつけ、付属の瞳用デカールシールを貼った。その後、ぼんやりと光って見えるように裏側をシルバーで塗り込む。塗装で一番難儀したのは、色の組み合わせではなく、雑に塗ったように見せることだった。現場スタッフが撮影の合間にペンキでペタペタと補修したように見えるよう、筆のタッチを工夫しながらやってみた。初めてのわりには上手くいったようにも思えるが、冷静にみるとこれもまだまだ発展途上だ。塗装全般、日々精進あるのみである。
こうして完成したヘドラ。本当ならヘドラのデザインをされた美術監督の井上泰幸氏の展覧会に持ち込みたいところだったが、流石は大物、そう簡単に持ち運び出来るような代物ではなかった。下手に持ち上げるとヒレが折れたり外れたりしてしまう。残念だったが今回は見送ることにした。代わりに写真を沢山撮ったので、お弟子さんの三池さん、井上さんの姪御さんである東郷さんにお見せすることにしようと思う。
| 全高 |
パーツ数 |
付属品 |
材質 |
| 375mm |
99点 |
瞳のデカールシール |
ウレタン樹脂 |
| 原型師 |
|
|
|
| 杉田 知宏 |
|
|
|
|